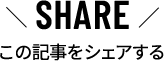CATEGORY : 知る
CES 2020で見えたAR・VR技術の飛躍的進化とその実力

VR(仮想現実)とAR(拡張現実)にとってここ数年は厳しい年が続いていました。消費者の関心と売上は伸びているにも関わらず、評論家たちはVRは“死んだ”と決めつけようとし、高額で実際には使用する機会が限られているARヘッドセットは、 “ビジネス向け”のニッチなアプリケーションへと開発が限定されていく傾向にありました。懐疑的な見方が正しければ、VR、ARそしてMR(複合現実)を含むいわゆる「XR」はいつ廃れても不思議ではない、一時的な流行だったということになります。

しかし2020年のCES(Consumer Electric Show)は反VR・AR派が(私から見れば救いようもないほど)間違っていたことを証明しました。ラスベガス・コンベンション・センターの北・中央・南ホールのそこかしこで、おなじみのブランドだけでなく様々な出展者がXR技術に関連する取り組みを展示していました。主要な自動車メーカーから比較的規模の小さい開発会社、動画配信会社などもVR・ARソリューションを大いにアピールしていましたが、本当に興味深い提案が数多くありました。CESでは最先端のXR技術を体験するのに現実世界を何キロも歩くことになるのですが、それを含めても私がこれまで参加した中で文句なしに最高のVR・AR展示会だったと言えます。
ここからは2020年のCESで目にした最も興味深いVR・ARの事例を紹介します。
【VR・AR】自動車産業向け
上の写真を見ればCESのVR展示ブースの様子が分かるでしょう。今年はブースごとにヘッドセットが一つだけ設置されてあったり、展示スペースの片隅でデモが行われているのではなく、何人もの人が一緒に最新のイノベーションを“体験”できるよう工夫されていました。
例えばヒュンダイのブースでは、ワイドスクリーンのVRヘッドセット「Pimax」を8台設置して空飛ぶタクシー「S-A1」のバーチャル試乗を体験できました。下の写真で天井からつり下げられているのは「S-A1」の実物大模型です。CES 2020では自動車メーカー各社がVRの体験コンテンツを用意していましたが、これはその一例です。リアルではなくバーチャルな体験を提供することで、ヒュンダイは非常に実用的なVRの使い方を提案していました。

上: ヒュンダイの空飛ぶタクシー「S-A1」の実物大模型を見て驚く大勢の来場者。一度に8名がVRヘッドセットを使って空飛ぶ“ウーバー”をバーチャルに体験することができました。
クレジット:Jeremy Horwitz/VentureBeat
これに匹敵するものとしてはホンダの展示が挙げられます。当初、VRのドライビングシミュレーターかと思ったものは、今後15年の自動車の進化をテーマにした9分間のVR映像コンテンツでした。ホンダは3Dのアニメ風映像を使って、コネクテッドカー技術を活用して安全でスムーズな交通の実現を目指す「SAFE SWARM」や、車の窓ガラスをディスプレイ化してインターネットで買い物ができたり、乗客の“心を落ちつかせる”宇宙の景色を表示したりできる新技術を展示していました。

またアウディのブースに足を運ぶと、一見しただけでは絵空事としか思えないような技術を目の当たりにすることができました。車の窓ガラスがビデオスクリーンとして機能しているのですが、このスクリーンも見掛け倒しではありません。車の走行に合わせて、ARのアイコンがスクリーン上に現れる仕掛けで、充電スタンドや観光地などの見所をリアルタイム表示し、ドライバーに教えてくれます。また乗員の体調を分析して、呼吸のエクササイズを薦めるなどウェルネス機能も搭載されていました。

ユーザーの視界に情報を投影するディスプレイ技術においては、別の技術提案もありました。前述のアウディのもう一つの展示では、視線追跡カメラが左右の目の焦点位置を検出し、ドライバーが視野に捉えている対象をARの3Dディスプレイとして視線の先に浮かんでいるように表示する技術を展示していました。今回は動画のみでの紹介でしたが、実際にはARヘッドアップディスプレイに用いられることになるでしょう。
今回のCESではヘッドセットの不要な裸眼での3D ディスプレイの展示も数多く行われていましたが、これについては別の機会にお伝えできればと思います。自動車業界では眼鏡や手袋を装着することなくドライバーが車載ARの利便性を享受できることが不可欠であるため、裸眼3Dディスプレイの重要性がことさら強調されていました。
【VR】コンシューマー/ビジネス向け
現時点でコンシューマー向けVRにおける2強はソニーとフェイスブックですが、両社ともに今回のCESでは新商品を発表していませんでした。その代わりにソニーは有線型VRヘッドセットとしては他の追随を許さない累計販売台数500万台を誇る「PlayStation VR」 の最新版のロゴを発表しました。これに対してフェイスブックは、2019年度の年末商戦では定価のままで売り切れが続出した「Oculus Quest」の人気に満足しているようでした。

2019年のCESで発表された「Vive Cosmos」ヘッドセットが全体的に不評だったため、開発元であるHTCは今年の参加を見合わせました。つまり今年はコンシューマー向けVRの大手企業はどこも新しいハードウェアを出さなかったということになります。しかし、その他の企業は興味深いテクノロジーを提案していました。

例えばAR・VRを専門とするテック企業、ノロは、既存のスマートフォン、PC、ヘッドセットに対応した6DoFコントローラーを発表しました。価格は200ドルで、VR配信プラットフォーム「SteamVR」のゲームをプレイ可能にするモーショントラッキング・キットが付属しています。今後5Gを使ったクラウドVRゲームが普及してもこのキットで対応できるということです。

またbHapticsは499ドルの「Tactot」ベストを含むウェアラブル触感型アクセサリーの「Tactsuit」シリーズを発表しました。このベストを着てパワフルに振動するパーツを胸部に装着すればSWATチームの一員のように屈強な体格になれます。バトルロイヤルゲーム「PUBG」の音楽をプレイしながら試着してみたところ、どんな体型でも着られるフリーサイズのデザインとはいえ、上半身全体で強力な衝撃を体感することができました。2020年後半には話題沸騰必至のVR版PUBGがリリースされる予定ですが、同社は現在このゲームのソフトウェアサポートに向けた取り組みを行っているそうです。

ビジネス向けVRも順調に進化しているようでした。なかでもPimaxとVRgineersの2社が “8K”(実際には片目4K)の驚異的な高解像度を持つVRヘッドセットを発表していました。これらはビジネスユーザーだけでなくパイロットや宇宙飛行士などの要求レベルが最も厳しい顧客層を想定して開発されています。VRgineersは新製品「8K XTAL 」ヘッドセットをアメリカ空軍が発注したことを宣伝していましたが、空軍関係者がPimaxの「Vision 8K X」の展示を吟味している姿も見受けられました。

一つのレンズで対象を完璧に表現するためのデータを捉えることは不可能ですが、この2社のデバイスは少なくともディスプレイに網目模様が見えてしまう“スクリーンドア効果”を排除することに成功しています。さらにユーザーの視線が集中する中心部分のみを高解像度で表現し、その他の部分を低解像度で描画する“中心窩適応レンダリング”をオンにすると、個々のピクセルだけが見えるよう工夫されていました。写真上のXTALと下のPimax(TV画面上に表示されている様子)の双方を検証してみたところ、ビジネスや軍事関係など最も目の肥えたユーザーでも、これらの新しいソリューションの鮮明な画像に感動するに違いないと思いました。

その他のVR系企業はビジネス向けデバイス開発の分野で自社の地位を確立しようと躍起になっていました。例えば中国のPicoは「Neo 2」 ヘッドセットを発表しましたがTobiiのアイ・トラッキング技術を搭載したものとそうでないものがあり、低価格で多用途の可能性を提供できることからHTCの「Vive Pro」や「Vive Pro Eye」に競合する商品になるでしょう。

また日本のパナソニックは小型軽量が特徴であるVRグラスのプロトタイプ(写真上)を発表しました。一般消費者ではなくビジネスユーザー向けの製品のようですが、コンセプト段階より先に開発が進まない可能性もあります。このサイズを実現するため、2019年のCESで発表した、自社製の極小マイクロ・ディスプレイを採用しています。理論上はこのディスプレイでもHDRカラー処理を利用できますが、視野は非常に限られています。パナソニックの担当者から具体的な情報を聞き出すことはできませんでしたが、まだはっきりとした計画がないのかも知れません。このプロトタイプが実際に商品化されるかどうかは今後に注目です。
【AR】コンシューマー/ビジネス向け
後世になってCES 2020を振り返る時、現実味のあるコンシューマー向けAR製品が初めて世の中に出た—言い換えればSF映画にありがちな類いや3,500ドル(約40万円)もするHoloLensのヘッドセットではなく、多くのユーザーの手が届く価格帯になった—のはあの時だったと思い返すことでしょう。
数多くの企業が500〜600米ドルの多機能ARグラスを展示していましたが、どれも2020年の夏までにリリースされるということでした。このイノベーションに拍車をかけた決定的な要素は、ARの情報処理にスマートフォンを利用する代わりに、ヘッドセット本体を軽量化し、センサー、カメラ、3次元ディスプレイを搭載したことです。この試みをQualcomm は “XR Viewers” または“XR Smart Viewers” と呼んでいました
Nrealが発表した「Light 」ARグラスや「Nebula 3D AR UI」は非常に好印象でしたがこれについては割愛し、2019年度の展示会で数多くのARハードウェアをトライした経験を踏まえてARのより大きな未来図について触れたいと思います。端的に言うと、2019年のCES以来、ARは大きな進化を遂げましたが、2021年までに一般消費者の利用がどれだけ拡大するかは未知数です。

上:Nrealの「Light」 ARグラスはデザインと性能の双方を高い次元で確立しました。これに追いつこうと競合他社も開発を進めています。
クレジット:Jeremy Horwitz/VentureBeat
コンシューマー向けAR製品を開発している企業の多くは中国系ですが、次から次へと市場に登場するこうした製品の中でもベストの地位を占めるのはやはりNreal の「Light」でしょう。まずNrealがあり、良くて“似たようなアイデア”に基づくものから、悪いものでは“コピー商品”まで多種多様にありますが、デザイン、装着感、視覚的性能、そしてソフトウェアサポートまで全てが揃っているのは「Light」だけです。MadGazeや0Glassesなど他ブランドの類似品を色々試してみて感じたのは、2020年の市場はそれなりに軽量なARグラスは多く登場するでしょうが、それでもNrealの製品は他を圧倒し続けるということでした。

上: Nrealの「Light」にそっくりの「RealX」を展示した0Glasses。しかしその性能はNrealの足元にも及びません。
クレジット:Jeremy Horwitz/VentureBeat
コンシューマー向けにARを開発する企業の間で話題に上っていたのは、アップルが2020年中に市場参入する可能性は低く、先行ブランドに対して約2年ほどの遅れを取っているだろうということでした。アップルのAR開発の問題や遅延についてはこれまでも報道されているので驚くにあたりませんが、アップルがテクノロジーとデザインの完璧に近い組み合わせを見出しかつそれを大量生産することが可能になるまで静観する姿勢を構える中、先行して開発を行うテック企業はいち早くファンを獲得し、消費者がARに対して持つイメージを意図的に作り上げていくこともできます。
私が試してみた限り、現段階のコンシューマー向けARグラスの問題は装着感です。ある程度予想通りとはいえこれは非常に重要です。CESでトライしたARグラスの大半は一定の角度で映像を投影するため、鼻が低い人なら大丈夫でも鼻が高い人が AR拡張された部分を見るために不自然にメガネを傾けたりする必要がありそうです。そうすると拡張部分が上か下にずれて見えたり、メガネにアイ・トラッキングカメラが内臓されている場合は目の動きを正確に捉えられないという状況が起こるかもしれません。
またVRシステムのもう一つの課題は、人によって異なる両目の間隔にディスプレイを合わせるために水平瞳孔間距離(IPD)を適切に設定することです。今のARグラスは比較的頭の大きい人にも合うフレームサイズ、重さやケーブル位置を調整可能にするだけでなく、視点の垂直方向の位置調節も一つの問題となっているのです。

上:Nebulaのインターフェースは正対して見るとホームスクリーンのように見えますが、アイコンやテキストは立体なので3D空間を歩き回ってもあらゆる角度から見ることができます。
クレジット:Nreal
ARグラスのさらなる懸念はルーム・スケール・トラッキングシステムの性能です。VR用のOculus Questのように空間構造を正確に3Dマッピングし、ユーザーの正確な現在位置に関連付けられたコンテンツをインターフェースに表示できれば大変な進歩です。例えばNreal 「Light」の「Nebula」システムを試した時、私はこのプロダクトの(かっこいい!)デザインの背後を見るために、沢山のアイコンやテキストが表示されている“ホームスクリーン”インターフェースの裏を物理的に歩くことができました。しかし、このルーム・マッピング機能がコンシューマー向けやQuestの製品で実際に機能するかどうかはまだ分かりません。

上:MadGazeはハンド・トラッキング技術を活用した音楽ゲームで「Glow Plus」ARグラスを売り込もうとしていましたが、私が試した時はトラッキング機能が上手く作動しませんでした。
クレジット:Jeremy Horwitz/VentureBeat
AR企業はインプット・ソリューションの進化にも取り組んでいます。Nrealは実際に利用可能なあらゆるオプションを試していることをオープンに認めています。Nrealのコンシューマー向けARグラスでは、スマートフォンを3DoFコントローラーとして使い、ポインタを動かしたりすることができます。また目と手の動きのトラッキングにはデバイス本体に搭載されたカメラを使い、サードパーティーの6DoFアームセンサー(写真下)やコントローラーに対応する予定です。逆に1〜2つのインプット方法に限定しているその他のARグラスデベロッパーたちはあまり良い結果を出せていない印象でした。

今回、私はビジネス向けARソリューションの展示にあまり時間を割きませんでした。2019年と2020年でデバイス自体がそれほど進化しなかったことと、ビジネス向けARに強いマイクロソフトとマジック・リープが出展していなかったことが主な理由です。少なくとも私が訪れた(数多くの)ブースでは、HoloLensやMagic Leap Oneのハードウェアを使っているところは一つもありませんでした。これは、少なくとも2~3の有力企業がこれらのデバイスを使ったデモを展示していた2019年と大きく異なる点です。

Vuzixが発表したビジネス向けARヘッドセット「M4000」は、既存製品のM400に似ていますが、完全に透明の(そしてより高価な)光導波路ディスプレイが採用されています。今回のCESではこのように製品をアップグレードした会社が大半を占めていました。M4000のセールスポイントは特定の業界のニーズに応えた比較的控え目のARグラスであること。一方でM400は今後も法人顧客のニーズに応えていくことでしょう。

上:側面のプロジェクターが映像光をレンズに出射するSyndiantの導光板ディスプレイ。正しい角度と距離から見ると縦線が映像に見える。
クレジット:Jeremy Horwitz/VentureBeat
これからのARソリューションでは導光板ディスプレイ技術が一般的になると業界内で言われていることから、ディスプレイメーカーのSyndiantに2020年製品の価格設定や性能の違いについて聞いてみました。担当者によると、導光板ディスプレイの価格は、そうでないものと比較して最低でも15〜20%ほど高くなっています。しかしマルチレイヤーディスプレイに匹敵する、あるいはそれを上回る解像度やディテールが欲しいならば、価格は一気に50%〜100%アップしてしまう、とのことです。つまり、コンシューマー向けARヘッドセットに導光板ディスプレイが標準装備されるのはまだまだ先のことになりそうです。
まとめ
CESは業界限定の超巨大イベントであり、一人の人間がその全体像を把握することは非常に難しいので、AR・VRの展示を全部見ようとわざわざラスベガスまで行くことはお薦めしません。とはいえ、コンシューマー/ビジネス向け市場、AR/VR、グラスあり/なしの3Dディスプレイのいずれかに興味を持っている人にとっては、2020年のCESは最高に素晴らしいXRの展示会だったと言えるでしょう。
ARのハードウェア、ソフトウェアだけでなく全体的なユーザーエクスペリエンスが日々進化してきた結果、次第に本格的な実用段階へと向かいつつあることを実感できました。またコンシューマー向けデバイスから小売りやビジネス向けへとVRの用途が徐々に拡大されていくことも現実味を帯びてきました。今回のCESが何かの指標であるとすれば、2020年はXRにとってとても刺激的な1年になるだろうということでしょう。今後の進展が非常に楽しみです。
この記事はVentureBeatのジェレミー・ホーウィッツによって書かれたもので、NewsCredパブリッシャーネットワークによってライセンスされています。ライセンスに関する質問については、legal@newscred.com.までお問い合わせください。