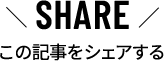CATEGORY : 知る
いわき市とタッグを組んで「常磐もの」の魅力をサッポロビールが発信! 関係者の皆さんにお話をうかがいました!【後編】

東日本大震災をきっかっけに元気を失っている「常磐もの」を元気づけようと、いわき市中央卸売市場の水産卸会社であるいわき魚類様にもご協力いただきながら、いわき市様とサッポロビールがプロモーション活動を展開しています。常磐ものの魅力や現状、そしてプロモーション活動のきっかけやについて、関係者の皆様にお話をうかがいました。前後編の2回にわたってお届けするインタビューの後編と、キャンペーン景品のオリジナルビール制作にあたって開催された試飲会の模様をお届けします。➡前編を見る!
■サッポロビールが「いわき常磐もの」の魅力発信をサポート
沖合で寒流の千島海流(親潮)と暖流の日本海流(黒潮)がぶつかり合い、豊かな漁場を形成しているため、いわき市周辺で水揚げされる魚はかねてより「常磐もの」と呼ばれ、築地市場などで高く評価されていました。
2015年にいわき市はこの呼び名を地域ブランドとして立ち上げ、プロモーション活動を行ってきました。サッポロビールはこの2024年からいわき市や、いわき市中央卸売市場の水産卸会社であるいわき魚類様とともに、この活動に携わっています。飲食店様で料理の素材として使っていただいたり、小売店で大々的に売り出していただいたり、SNSを使ったキャンペーンも展開したりと、首都圏をターゲットにさまざまなアプローチで常磐ものの魅力を発信しています。
文中に登場しないかたもいらっしゃいますが、前編同様、以下の皆さんにお話をうかがっています。
いわき市農林水産部水産振興課 課長 松田浩一さん農林水産部水産振興課 統括主査 安藤成央さん農林水産部水産振興課 主査 鈴木浩美さん | いわき魚類代表取締役社長 鈴木健寿さん常務取締役 金成裕司さん塩干部 合物課 多田義典さん | サッポロビール新規事業開拓部地域創生事業グループ リーダー 和田龍成新規事業開拓部地域創生事業グループ リーダー 丸山創サッポロホールディングス経営企画部新規事業準備室マネージャー 保坂将志 |

■環境の変化で常磐ものの内実にも変化が
――近年は環境の変化で捕れる魚の種類や時期が変わってきていると言われていますが、常磐ものも旬が変わってきたりもしているんですか?
いわき魚類 鈴木健寿さん(以下、鈴木社長):たとえばいわきを代表する魚のひとつであるヤナギガレイは、以前だったら11月頃に子持ちのものがとれたんですよ。今は12月でもあまり子持ちがいなくて、年が明けてから数が出てくるようになったりとか。そうするとお歳暮の時期も外れてしまうので、あまり高値で取引できなくなってきています。
それと、本来だったらもっと南のほうでしかとれなかった伊勢エビやトラフグ、カマスなんかが、近年ではこの辺りでもとれるようになってきましたね。
――そんなに環境が変わってきているんですね。そうすると冬場のおいしい魚も変化してきているんでしょうか?
いわき魚類 金成裕司さん(以下、金成常務):そこはあんまり変わっていなくて、やっぱり冬においしい魚といえば、ヒラメとアンコウじゃないですかね。
鈴木社長:この辺りのヒラメは飴色の身をしていて、活〆にするとおいしいんですよ。私は寝かせて熟成させるよりだんぜん活〆が好きです。
金成常務:活〆もおいしいけど、やっぱり私は昆布締めがいいな。今は昆布締めをする家庭もあまりないかもしれませんが、年配の人はよくヒラメの昆布締めをつくりますね。


■高い技術に裏打ちされた高品質ないわき市の加工品
――もうお話をうかがっているだけで、よだれが出てきそうなお話ですね。先ほどから何度か加工品のお話も出てきていますが、加工品については何が有名なのでしょうか?
鈴木社長:干物から練り物から加工品全般です。というのも、いわき市の加工業者は技術がとても高いんです。加工業者はいわきでとれた魚だけでなく、輸入した材料でもいろいろな加工品をつくっています。たとえばタコはアフリカなどいろいろな国から輸入されてきたものを、塩で揉んで茹でて出荷します。そう聞くと簡単そうに思えるかもしれませんが、産地やシーズン、大きさなどによって、いろいろとやり方を加減しないと1年を通じて安定した品質のものはつくれません。
これはかまぼこなどの練り物にしても、干物にしてもそうで、同じ原料と同じ機械を与えられても作り方ひとつでまったくの別物になってしまいます。
――なるほど、加工品に関してはどれがおいしいという話ではなく、いわき市を中心としたエリアは技術の高い加工業者が多いから加工品の種類も多いうえにどれもおいしいということなんですね。
いわき市 松田浩一さん:ちなみにサンマのみりん干しはいわきが発祥の地ですね。
鈴木社長:イワシが大不漁だった年にたまたまサンマがたくさんとれて、それを加工したのがはじまりですね。
鈴木社長:しかし、みりん干しは加工業者の数も震災ですごく減りました。震災で設備が壊れてしまった加工業者はすごく多かったんです。
金成常務:この地域では個人経営の魚屋さんでもその店ごとの味付けでみりん干しをつくって販売していました。それくらい魚の加工技術が高い土地なんです。
――店ごとに違う味付けのみりん干しがあるって、好きな人にとっては夢のようなお話ですね。
金成常務:今でも自分たちでみりん干しを作っている魚屋さんはあって、自慢の味として売り出していますよ。


■水産加工業者への恩返し
――プロジェクトのベースとなった案をつくられた多田さんは、この事業がはじまる前は水産加工会社にいらしたそうですが、鈴木社長が多田さんの引き抜きを決意されたのはどんな理由からですか?
鈴木社長:加工屋さんにいて描ける絵と、うちみたいな流通を担っている会社で描ける絵はぜんぜん違います。関係する業者の数、チームの組みかたとバックアップ体制、使える経費と状況が大きく変わりますからね。うちに入ったほうが実現する可能性は確実に高まると考えたんです。
水産加工業者は規模の小さいところも多いから、付き合いのないところにいきなり話を持っていってもサッポロビールの名前が大きすぎて尻込みをするところも少なくないはず。いわき魚類があいだに入ることで、そういった企業に安心感を与えることもできますね。
サッポロビール 和田龍成(以下、和田):僕らはビールのメーカーなので、物流や商流にまったく入らないんですよ。しかし今回はいわき魚類さんに流通の部分を担っていただけたのは本当に心強かったです。
鈴木社長:多田からの相談は、BtoB、企業間での取引という視点がありました。苦戦している加工屋さんとうまくつなげられれば、雇用も増えるし、水産業全体が盛り上がります。
いわき魚類 多田義典さん(以下、多田さん):水産業において、おそらく一般のお客様が考えられている以上に加工屋さんは大事な存在なんです。というのも、魚が一度に大量にとれたときに、加工屋さんがたくさん原料として使ってくれることでその魚があまり値崩れを起こさずに済むんですね。
鈴木社長:震災後、しばらく魚がとれなかった時期を僕らは水産加工品を売ってしのぎました。あのときの恩返しをしたいという想いも僕らはずっと抱いているんです。この事業が少しでも加工屋さんへの恩返しになればうれしいですね。

■お客様に食べていただくまでを見届ける
――これまでのお話で、いわき市やいわき魚類のかたからサッポロビールの提案は現場を考えたものになっていたとご評価いただいているのがわかりました。サッポロビールとしては、どのような想いでこれを提案したのでしょうか?
和田:当事者でない我々が関わるときには、やはり福島のかたがたの想いに寄り添うことが大前提だという考えがまずありました。ALPS処理水の話にしても、震災後の東北の水産物に関しては、当事者でない人たちばかりがネガティブな論調で騒いでいるように感じられていたんです。いざ福島に来てみると、いわき市の水産事業者さんは、家族を守り、生活を営んでいくために、目の前にある安全でおいしい魚をお客様に届けるという仕事をひたすら実直にこなしていました。
一時の売り上げを伸ばすのではなく、常磐ものが当たり前の「おいしいブランド品」として、当たり前に流通していくこと。いろいろお話をうかがっているうちに、これがいわきの水産事業者さんたちの願いであることがわかりました。なので、我々としては、売って終わりではなく、しっかりお客様の口に入るまでを見届けられるような工夫を大事にしようと決めたんです。
ロゴシールが貼られた海産物を店頭に並べて終わるのではなく、常磐ものの魅力がさらに際立つように、しっかりした技術をもつお店でよりおいしく召し上がっていただき、その魅力を存分に感じてもらいたいと考えています。
――どんな飲食店さん、小売店さんと組んでプロモーションを展開するかは決まっているんですか?
和田:飲食店さんについては、首都圏等で人気の飲食店を展開しているエー・ピーホールディングスさんの四十八漁場や、都内の有名レストランであるラフィナージュさん、サーラアマービレさんのようなトップクラスのレストランも協力してくださることになっています。
小売店さんについては百貨店やショッピングモールで店舗を展開している鮮魚専門店の中島水産さんにご協力いただき、しっかりお客様に常磐ものを届けていただきます。

■サッポロビールはなぜ地域創生事業を手がけるのか?
――サッポロビールはなぜ専門の部署をつくってまで地域創生事業に取り組んでいるのでしょうか?
サッポロビール 丸山創:スタートは外食営業からはじまった話です。どうやったらサッポロビールを選んでもらえるのかを考えたときに、「ビールを売るためにビール以外のものをサポートする」という手法を以前からとってきた経緯があるんです。たとえばお店を開業するときに、物件や人材を紹介するなどといったことですね。
その延長線上として、飲食店さんとのネットワークを使えば、地方自治体や生産者さんたちが自信を持って世に送り出そうとしている商品を、首都圏や近畿圏の飲食店さんに売り込むことができるのではないかと考えて立ち上がったのが、我々地域創生事業グループです。
我々としても、また地方の生産者さんにしても、販路の拡大につながるんじゃないかという期待を込めてスタートしたんですね。ただそれだけで終わらず、飲食店さんにいい素材を使った料理で繁盛してもらい、そのお供としてサッポロビールを飲んでいただくことで、関わった人たちすべてが喜べる状況をつくるのが最初のゴールでした。
でも最近の立場としては、ビールを売ることはもちろんですけど、それよりも、我々も自信を持って紹介できるいい飲食店さんに、いい素材を使ってもらいたいという想いを強く持って事業に取り組んでいますね。
■常磐ものを理由に選んでいただけるように
――最後にこのプロジェクトにどんなことを期待されているのか、聞かせていただけますか?
和田:飲食店にも、一般のお客様にも、とにかくひとりでも多くのかたに「常磐ものはおいしい」と広く知っていただけたらいいですね。
鈴木社長:なるべく多くの人に「常磐ものが好き」と思わせられる事業にしたいですね。
いわき市 安藤成央さん:我々行政サイドとしては、かまぼこでも干物でも刺身でも、店頭でいろんなものが並んでいたときに「こっちにしよう」と常磐ものを選んでもらえるようになって欲しくてこの事業を進めています。今回はいわき魚類さんという地元企業とサッポロビールさんといわき市の三者がうまく手を取り合って常磐ものの魅力を広く知ってもらおうと動けている実感はありますね。
鈴木社長:スーパーの鮮魚売り場でこのロゴを見たときに、飲食店で食べたときの「おいしい」という記憶がきっかけになって選んでもらえる。あるいは逆に、スーパーで買ったおいしい魚に貼られていたロゴを飲食店で見かけて、それを理由に料理を頼んでみる。そんな状況になってくれるとうれしいですね。
――おいしいと広く知られるだけでなく、「常磐ものだから」と多くの人から選ばれるようになるのが目標なんですね。インタビューへのご協力、ありがとうございました。




■常磐ものをより楽しむために、特製オリジナルビールも開発!
インタビューを終えた後、インタビューの参加メンバーによって、ビールの試飲会が開催されました。今回のプロジェクトでは、飲食店で常磐ものの料理を食べたお客様や、小売店で常磐ものを購入されたお客様を対象に、XとInstagramを活用したキャンペーンも開催されます。その景品のひとつとして予定されているのが、「常磐ものに合うオリジナルビール(JOBAN BEER)」。
サッポロビールの協力工場にて生産されるこのオリジナルビールを、どんなスタイルでどんな味わいにするべきかを決めるにあたり、その意見を試飲会で広く集めようというわけです。
ご協力いただいたのは、いわき魚類の若手社員の皆さん。常磐ものの名物のひとつ、あんこう鍋とともにビールを試飲していただき、その感想をうかがいました。ちなみに試飲していただいたのは、ゴールデンエール、ホワイトエール、IPA、黒ビールの4種類。これら4種のビールをベースに、実際の景品となるオリジナルビールが開発されます。
独特の食感を持つあんこうの身を、味噌仕立てでいただくのが、あんこう鍋。味噌の味わいが濃厚なだけに、さっぱりとした味わいのビールがいいのか? それとも、鍋に負けないしっかりとした味わいがいいのか? 味噌と黒ビールと香りの相性は? など、皆さん首を傾げたり、意見を交換したりしつつ、試飲を続けます。なかには試飲の域を超えてぐびぐびと飲まれているかたも……。
はたして実際の景品となるビールはどんな味わいになったのでしょうか?


●「いわき常磐もの写真投稿キャンペーン」公式ページを見る
(文=稲垣宗彦)