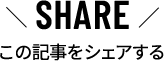CATEGORY : 知る
いわき市とタッグを組んで「常磐もの」の魅力をサッポロビールが発信! 関係者の皆さんにお話をうかがいました!【前編】

サッポロビールはさまざまな自治体と協力を結び、その地域の特産品をプロモーションする活動を展開しています。そのうちのひとつ、福島県いわき市の「常磐もの」のプロモーション活動について、前後編の2回にわたってご紹介します。今回は前編です。
■サッポロビールが「常磐もの」の魅力発信をサポート
沖合で寒流の千島海流(親潮)と暖流の日本海流(黒潮)がぶつかり合い、豊かな漁場を形成している福島県いわき市は、以前からおいしい魚が水揚げされることで、水産関係者や飲食店業界からは高く評価されてきました。
しかし、東日本大震災で状況は一変。残念なことに風評被害等の影響もあって未だに少し元気を失った状況が続いています。
そこでいわき市は2015年に地域ブランド「常磐もの」を立ち上げ、さまざまなプロモーション活動を展開してきました。2024年度のプロモーション活動のパートナーを公募した際、これにサッポロビールが立候補。提出したプロジェクト案をご評価いただいた結果、ともにいわき常磐ものの魅力を発信していくことになりました。
このプロジェクトには、首都圏のカジュアルレストランや高級レストランでお客様に常磐もののおいしさを知っていただくプロモーション活動や、鮮魚専門店でのフェア開催、SNSを活用したキャンペーン、さらにインフルエンサーやWeb雑誌による情報発信など、さまざまな施策が含まれています。
いわき市とサッポロビールが推進する今回のプロジェクトには、流通関係の担い手として、いわき市中央卸売市場の水産卸会社であるいわき魚類にもご協力いただいています。常磐ものの魅力やその現状とあわせ、今回のコラボレーションについて、関係者の皆さんにお話をうかがいました。
お話をうかがったのは、以下の皆さんです。

いわき市
農林水産部水産振興課 統括主査 安藤成央さん(右)
農林水産部水産振興課 主査 鈴木浩美さん(中央)
農林水産部水産振興課 課長 松田浩一さん(左)
 いわき魚類
いわき魚類
常務取締役 金成裕司さん(右)
代表取締役社長 鈴木健寿さん(中央)
塩干部 合物課 多田義典さん(左)

サッポロビール
新規事業開拓部地域創生事業グループ リーダー 和田龍成(右)
新規事業開拓部地域創生事業グループ リーダー 丸山創(左)
サッポロホールディングス
経営企画部新規事業準備室マネージャー 保坂将志(中央)

■そもそも「常磐もの」って?
――今回のプロジェクトのテーマとなっている「常磐もの」とはどういうブランドなのでしょうか?
いわき市 鈴木浩美さん(以下、鈴木[浩]さん):常磐という言葉は福島県沿岸と、茨城県の旧国名である「磐城(いわき)」と「常陸(ひたち)」から一文字ずつをとったもので、この辺りの地域を指す言葉です。福島県の沿岸部は浜通りと呼ばれていますが、昔から常陸から浜通りの辺りでは水揚げされる魚の種類が多いうえにおいしいと、評価がとても高かったんです。
いわき魚類 鈴木健寿さん(以下、鈴木社長):震災後にイメージダウンしてしまった福島の水産物を復興するのに旗印を作ろうっていう話が市から出ました。そのときに、プロ、つまり水産関係者の間だけで使われている「常磐もの」という言葉を見つけてきて、これをブランド化することにしたんです。
鈴木[浩]さん:平成27年、2015年のことなので、今年でブランド立ち上げから10年ということになりますね。
鈴木社長:そのときに、海産物を指す「物」と、人物を指す「者」のどちらの意味ももたせられるようにと、「もの」をあえてひらがなで書くことにしたんです。ここで水揚げされた鮮魚はもちろん、いわきで加工した海産物、さらにいわきで働く水産事業者などまで含めて「常磐もの」としてブランドを背負い、一丸となってイメージアップに努めています。
――駅前の商業施設にある魚屋さんに寄ったところ、常磐ものにはロゴが描かれたシールが貼られていました。一目でわかるようになっているんですね。
鈴木社長:あのロゴもけっこういろんなアイデアを詰めこんでデザインしているんです。常磐でとれる海産物の種類が多くておいしいのは、沖合で親潮と黒潮がぶつかるから。ロゴに使われている青と赤は、それぞれが親潮と黒潮を表しています。


■BtoBのビジネスとして常磐ものの販路拡大を狙う
――常磐もののプロモーションは2015年から行ってきたとのことですが、2024年の公募には何かこれまでと違う部分があったのでしょうか?
鈴木[浩]さん:2023年8月にあったALPS処理水の海洋放出による影響を最小限におさえることを目的として、復興庁の福島再生加速化交付金がいただけることになりました。そこで主に首都圏をターゲットとして、常磐もののおいしさを体験していただく事業を2023年度から2025年度まで3カ年の実施を予定しています。「イベントだから」と一時的に売れるのではなくて、商品の魅力を知ってもらって、「おいしいから売れる」ようにしたいというのが、我々の願いです。そのためにはPRイベントだけでもダメだし、単に商談会みたいなのを開いてもパンチに欠けます。
サッポロビールさんのご提案は、ビールでのつながりを活用して、流通業者と飲食店さんや鮮魚専門店などを結んで、持続性のあるBtoBのビジネスとして販路拡大を考え、まさに定期的に売れ続ける方策を考えてくれているんです。具体的に言うと、常磐ものの魚や水産加工品が豊洲市場を通じて首都圏に継続的に流通していくような流れを作ろうとしている点がほかと違っていました。
――サッポロビールからはBtoBのビジネスとしての提案があるとのことですが、具体的にはどういう違いがあるのでしょうか?
鈴木社長:ビールを卸す関係で飲食店さんとのつながりが深いんです。どこか会場を借りて開催するようなイベントではなく、ふだん行くようなお店で常磐ものを多くのお客様が食べ、そのおいしさに気づいてくださるような、自然な流れを考えてくれているのが僕らにとってはうれしいところです。
サッポロビール 和田龍成(以下、和田):生産者の方や流通関係者と同じ目線で提案書をつくれるというのは我々の強みでした。サッポロビールはほかにも地域創生に関わる事業をいくつもおこなっていますが、いちばん大切にしているのが“現場”です。ここで言う現場とは、いわきの海で働く漁師さんや水産加工業者さん、卸業者さん、ほかにも豊洲市場をはじめとする東京での流通関係者やバイヤー、実際に常磐ものを売る魚屋さんや飲食店さん、そして魚を食べてくださるお客様まで、常磐ものに関わるすべての人たちです。
こうした現場に関わる皆さんがWIN-WINになる取組にするために、我々は活動しております。
また、サッポロビールの地域再生事業グループ全員が同じように現場を大切にするという理念を持って仕事をしています。それがサッポロビールの強みですし、そこをご評価してくださったからこそ採択していただけたんだと思っています。
――お金をかけてイベントを開催してその場限りの売り上げを確保するのではなく、継続的に売れるものにしていきたいという皆さんの想いはとても強く伝わってきました。もともといわき市の沿岸は好漁場だったとのことですが、震災で漁獲量はどれくらい減ってしまったのでしょうか?
いわき市 松田浩一さん:現状では、いわき市の水揚量は震災前の4割ぐらいに落ち込んでいます。
鈴木社長:たとえばカツオなんかは、以前は中之作港と小名浜港で毎日100トンずつ、計200トンの水揚げがありました。小名浜と中之作は5キロメートルと離れていないので、ひとつの浜みたいなもの。そう考えると、気仙沼にも決して負けていないくらいの水揚げでしたね。

■一年を通じて魚の質の高い「常磐もの」
――それにしてもひとつの港で1日の水揚げが100トンって、本当にカツオがたくさんとれたんですね。
いわき魚類 金成裕司さん(以下、金成常務):いわき魚類ではカツオだけで売り上げの10パーセントを占めていたこともありますね。
――常磐もののロゴが先ほど話題に上りましたが、ロゴの中央に描かれている魚はカツオですか?
鈴木社長:常磐ものはカツオだけではないのでカツオであると明言はしていませんが、イメージしていることは確かですね。常磐もののカツオはやっぱりおいしいですから。
――常磐ものというと、中心となる魚は何になるんですか?
金成常務:カツオはもちろんですけど、ヒラメとかスズキなんかも上質ですね。スズキは日本一の高値で取引されています。ほかにはマコガレイとかも良い値段がつきますね。何か中心となる魚があるというよりは、魚種ごとに旬があって、一年を通じてそれぞれすばらしいものが水揚げされるのが、築地で常磐ものが高く評価されていた理由ですね。


■肩をとんとん叩いてはじまったプロジェクト
――いわき魚類がこの事業に関わるようになったのは、どういったきっかけからでしょうか?
鈴木社長:もともとうちのグループ内の水産加工会社にいた多田とサッポロビールの和田さんが「常磐ものをもっとたくさん売るにはどうしたらいいか?」とアイデアを以前から出し合っていて、それをいわき魚類へと持ってきたのがはじまりなんです。
いわき魚類 多田義典さん(以下、多田さん):僕と和田さんは「常磐ものをどうやって売るか」を考えていろんなところに片っ端から相談していたんです。相談したうちの1社がいわき魚類でした。
――いつ頃からアイデアを出し合っていたんですか?
多田さん:2月から和田さんと各所に当たってみましたがまったく話は進展せず、そもそも当時自分がいた会社を動かすことすら難しくて。ひたすら2人で挫折を味わっていましたね。そのうち仕事というよりも意地になっていて、最後の頼みの綱として鈴木社長に相談したところ、まだ具体的なことがなにひとつ決まっていなかったのに、快く「協力する」と言っていただけて。
――それがいわき魚類への転職につながるんですね。
多田さん:そうですね。でもそれがかえって「何かすこしでも形にしないと」というプレッシャーにもなりました。ちょっとはったりをかまして「和田さんと常磐ものを日本一売る」と社長には言ったんですけど……。
鈴木社長:そうやって無理に話を大きくすると歪みが出るからやめろ、と止めました(笑)。目の前の小さいことを着実に進めて大きく育てたほうがいいですからね。
多田さん:何も形にならなくて、それくらい必死になっていたんですよね。でも結果的に和田さんと話し合っていた内容が、サッポロビールが提出したプロジェクト案のベースになり、いわき市に採択される結果となりました。今はこうしてたくさんの人や会社にご協力いただけて、奇跡のようです。
――出発点となった多田さんとの接点はどのように生まれたんですか?
多田さん:とある福島県のイベントで、とつぜん肩をとんとんと叩かれて、「福島の魚を東京にたくさん売りませんか?」と和田さんが話しかけてきたんです。
和田: 福島県の水産物を売るためのビジョンを漠然と思い描きながら、いろんな水産会社の人の肩をとんとんたたきました。そのなかで、いちばん反応がよかったのが多田さんでした。
多田さん:僕には「僕にしか声をかけていない」ってずっと言ってたんですよ。今はじめていろんな人に声をかけていたと知って、正直びっくりしました。
――このインタビューは、【後編】へと続きます。➡後編を見る!
(文・写真=稲垣宗彦)