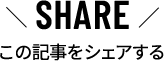CATEGORY : 遊ぶ
サッポロビールの歴史が詰まった本社周辺のスポットを社員が直接解説! 「恵比寿の街歩き」イベント開催!

恵比寿という街の名前はサッポロビールの工場があったことからつけられた――。ここをお読みの方にはもはや常識となっているかもしれない豆知識ですね。実はサッポロビールの本社周辺には、そのビール工場があった時代の記憶が刻まれたスポットがいくつも現存しているのです。サッポロビール社員の解説を聞きながらそうしたスポットを巡る「恵比寿の街歩き」イベントの模様をご紹介します。
■集合はサッポロビールの本社前
恵比寿ガーデンプレイスがある場所には、かつてサッポロビールの恵比寿工場があったことは、皆さんご存じですよね?
サッポロビールの前身である日本麦酒醸造会社がこの地に工場をつくり、ヱビスビールの製造を開始したのは1889年。以来、1988年までの約100年にわたってこの土地でずっとビールの醸造が行われていました。その工場跡地につくられた恵比寿ガーデンプレイスは、今から31年前の1994年10月8日に開業。サッポロビールはその開業より一足お先の同年9月に本社を中央区銀座からここへと移転させています。
ほぼ1世紀にわたってビールをつくり続けたこの土地は、サッポロビールにとって特別な場所。工場がなくなり、恵比寿ガーデンプレイスとなった際には、工場があったことを偲ぶ遺構などが保存されました。それを巡り、現在に至るヱビスビールの長い歴史に想いを馳せるのが、このツアーの目的です。ツアーの集合場所は、恵比寿ガーデンプレイスの北東にあるサッポロビール本社の前、兜煙突のところです。全4回にわたって催されたツアーでは、各回それぞれ約20人の方々にご参加いただきました。
まずは運営スタッフからのご挨拶とイベントの趣旨説明がなされたあと、各スポットの解説を担当するサッポロビール社員の自己紹介です。皆さんをご案内したのは、ヱビスビール記念館の元館長でありYEBISU BREWERY TOKYO統括マネージャーと、長らく千葉工場で工場見学のアテンドを務めてきた広報部の社員が交代で当たりました。いずれもサッポロビールの歴史に詳しい者ばかりです。それではツアーで巡った各スポットをご紹介していきましょう。

●街歩きスポットその1:恵比寿ビール醸造場創業当時の写真
本社社屋に向かって右手のほうには、四角い池があります。その池の脇にある壁には、恵比寿ビール醸造所が作られた当時の写真がペイントされています。
恵比寿ビール醸造所がつくられた明治22年、この醸造所一帯は東京府荏原郡目黒村三田という地名でした。当時、大きく需要を伸ばしていた外国産ビールに比べ、国産ビールは生産量も質も大きく劣っていたそうです。それを憂慮した東京や横浜の資本家たちは、東京で日本一のビール会社を目指し、日本麦酒醸造会社を設立しました。
当時の日本ではドイツ産のビールがとても人気だったことから、ビールづくりに必要な設備はすべてドイツから輸入。当時にして約6万円もかかったそうです。現在の貨幣価値に換算すると4億円を軽くこえるくらいの大金でした。当時はビールをつくれる日本人も限られていたため、ドイツから醸造技術者と助手、機械技師の3名を雇い入れたとのこと。写真をよく見ると背の高い人が混じっていて、それがドイツ人たちではないかと言われているそうです。
建物の前に並べられているのは、熟成用の木樽。人の大きさと比較して、1800リットルくらい入る大きさと推測されています。また、恵比寿駅から来るとよくわかるのですが、この一帯は高台になっています。地盤もよく、ビールを熟成させる地下貯蔵庫をつくるのに適した土地であることも、この場所が選ばれた理由のひとつだそうです。建物の右には山が見えていますが、これは富士山。建物がほとんどなかった当時は高台のこの場所から富士山が見えたのですね。
この醸造所でつくられたビールは工場ができた翌年、1890年2月25日に発売されます。当初は大黒ビールにしようとしていたそうですが、すでに横浜に大黒ビールというブランドが存在したため、混同を避けるためにヱビスという名前になった理由のひとつ。また、七福神のなかでは恵比寿さまが唯一、日本の神様であること、さらに五穀豊穣、商売繁盛の象徴であることにあやかってのことだそうです。


●街歩きスポットその2:馬越恭平の銅像
次に向かったのは、2024年4月にオープンしたYEBISU BREWERY TOKYO、ではなく、その入り口に向かって左手にある銅像のところ。もしかすると、YEBISU BREWERY TOKYOへ来たことがあってもここに銅像があることに気づいていない方もいらっしゃるかもしれません。 銅像は、日本麦酒醸造の4代目社長、馬越恭平をモデルにしたもの。前述のように、恵比寿ビールは1890年2月25日に発売されました。しかし、実はこのとき、日本では金融恐慌が起こっていました。せっかく発売にこぎつけた恵比寿ビールは、まったく売れなかったのです。
そこで日本麦酒醸造の経営に乗り出してきたのが、当時の大株主であった三井物産で大きな功績を挙げ、ナンバースリーの位置まで出世していた馬越恭平でした。1892年に日本麦酒醸造の重役に就任した馬越は、お金の流れをしっかり管理するとともに、ヱビスビールを売るためのアイデアをどんどん実行していきます。
その結果、たった1年で業績を黒字にし、経営を建て直すことに成功。サッポロビールにしてみれば、歴代社長のなかでももっとも長い任期を務めた馬越は、まさに「中興の祖」といえる存在。馬越は後に「日本のビール王」や「東洋のビール王」とまで呼ばれるようになりました。 このYEBISU BREWERY TOKYOの前に置かれた銅像は、馬越が満76歳、喜寿を祝ってつくられたもの。こうした生前につくられる像は寿像と呼ばれるのだそうです。
第二次大戦中は金属類回収令により、この銅像も供出することになったそうです。像から魂を抜く抜魂式まで行われたそうですが、今も現存している通り、回収はされずに終戦を迎えました。理由としては当時の日本のガソリン不足と「重すぎて運び出せなかったのではないか」と言われているそうです。 1900年のパリ万博に恵比寿ビールを出品し、30カ国以上から出品された他のビールを打ち負かし、金賞を勝ち取ったのも、当時の日本鉄道にかけあってビール専用の貨物駅をつくったのも、馬越の功績。日本で最初にビヤホールをつくったのも、この馬越恭平です。


●街歩きスポットその3:巨大な石碑
YEBISU BREWERY TOKYOの入り口に向かって右手側、馬越恭平の銅像と向かい合うような位置に、高さ約5メートルの巨大な石碑が建っています。3番目に訪れたスポットは、この石碑です。石碑の最上部には「国富の巨人」と文字が入っています。日本を富める国にした人、つまり馬越恭平を称えたもので、1844年11月21日(天保15年10月12日)に生まれてから、1933年(昭和8年)4月20日に没するまでの偉業が記されています。
日本麦酒醸造は、1893年(明治26年)に社名を日本麦酒株式会社へと変更。さらに1906年(明治39年)3月には、馬越恭平が中心となり、アサヒビールの前身である大阪麦酒、サッポロビールの前身である札幌麦酒と合併し、大日本麦酒へと生まれ変わります。馬越はこの大日本麦酒でも亡くなるまで社長を務めました。 馬越の没後は社長の座は空白の状態が続いていましたが、1933年から取締役会長に就任していた大橋新太郎がこの石碑を建てました。
大橋新太郎は明治から大正にかけて、出版、印刷、販売を手がけた出版界の成功者。衆議院議員や貴族院議員も務めた人物です。

●街歩きスポットその4:醸造棟のレンガ
石碑のわきの階段をのぼり、一行は次のスポットを目指し、恵比寿ガーデンプレイスの南から東を囲むように走るプラタナス通りへ。 恵比寿ガーデンプレイスの南端のほうを見渡せる位置まで来たときのこと。先に壁にペイントされた写真で見た恵比寿ビール醸造所の建物がつくられた場所について、ガイド役のサッポロビール社員から追加の解説が加えられました。
正確な資料が残っていないために写真からの推測でしかないそうですが、シャトーレストランのジョエル・ロブションか、東京都写真美術館がある辺りにつくられたのではないか、とのこと。当時はその辺りから富士山が見えたということですね。 そして4番目のスポットは、プラタナス通りに出てから左に曲がってすぐのところにあります。明治41年頃に建てられた醸造棟に使われていたレンガです。
レンガにはいろいろな積み方がありますが、この醸造棟で使われていたのは、イギリス積みという技法。直方体をしたレンガには、長手と呼ばれる長い面と、小口と呼ばれる短い面があります。イギリス積みでは、長手だけの段、小口だけの段を一定間隔で交互に積み上げていきます。 他の方法よりも少ないレンガで頑丈につくれるうえ、手早く積めるのがイギリス積みの長所。たとえば札幌ビール園など、サッポロビール関連の施設でレンガ積みが残っているところはすべてこのイギリス積みが用いられているそうです。
恵比寿ガーデンプレイスの北西の角、恵比寿駅からのびるスカイウォークの前の横断歩道をわたったとろに、レンガづくりの3階建ての建物、エントランスパビリオンがあります。1階にYEBISU BAR STANDが入った建物といえばすぐにわかる人もいるかもしれませんね。実はこのエントランスパビリオンはまさに当時の醸造棟を模してつくられているのだそうです。


●街歩きスポットその5:恵比寿神社
プラタナス通りから木々のあいだにある小路を入ったところが、次の目的地、恵比寿神社です。先述の馬越恭平が1894年(明治27年)全国のえびす神社の総本社である西宮神社(兵庫県西宮市)からご分祀をうけ、工場内に祀ったのがこの神社のはじまりです。 当時は現在のエントランスパビリオンのあたりにあったとのこと。恵比寿ガーデンプレイスの竣工にともない、現在の位置に神殿を建立し、今に至るのだそうです。
ここでガイド役の社員が1枚の写真を取り出しました。恵比寿神社ができた3年後、1897年(明治30年)頃に撮られたその写真には、恵比寿神社の神殿を背景に2人の人物が写っています。そのうちの1人はのちに常務取締役にまで出世した橋本卯太郎という人物です。 橋本卯太郎は冷凍技術の機械技師で、冷凍技術の第一人者とまでいわれていたと言います。当時の醸造所でつくられていたラガービールは発酵や熟成の際に冷却する必要があるため、冷凍技術が不可欠だったのです。
橋本卯太郎は写真を撮るのが趣味だったそうで、YEBISU BREWERY TOKYOのミュージアムエリアには彼が撮影したものが何枚も展示されています。ちなみに橋本卯太郎が写ったこの写真の撮影者はといいますと、なんと徳川慶喜公。最後の将軍として知られる慶喜公は、橋本卯太郎とは写真撮影という同じ趣味を持つ友だちだったそうです。
ちなみにこの橋本卯太郎は第82・83代内閣総理大臣を務めた橋本龍太郎氏の祖父にあたります。

●街歩きスポットその6:2体の銅像
恵比寿神社からサッポロビール本社の表玄関方向へ小路を進んだところに、銅像が2体建てられています。向かって右側が、高橋龍太郎、左側が柴田清の銅像です。先述のように日本麦酒醸造はその後、日本麦酒へと社名を変え、さらに大阪麦酒や札幌麦酒と合併し、大日本麦酒となりました。その初代社長に就任し、亡くなるまでずっとその役職を全うしたのが馬越恭平です。
その馬越の次に、2代目の社長に就任したのが、高橋龍太郎です。馬越が亡くなったのが1933年、高橋龍太郎が社長に就任したのが1937年ですから4年もの間、社長の座が空白だったことになりますね。日本のビールシェアの7割を占めていた大日本麦酒でしたが、第二次大戦後は財閥解体のあおりを受け、解体に。朝日麦酒(現アサヒビール)と日本麦酒(現サッポロビール)の2社へとわかれ、高橋龍太郎は日本麦酒の役員に就任しました。
高橋龍太郎は戦中戦後の大変な時期を社長として大日本麦酒を率いた功績もさることながら、現在の千葉ロッテマリーンズへとつながる高橋ユニオンズのオーナーを務めたり、また、第3代日本サッカー協会会長を務めたりと、本業以外の部分でも活躍したことで知られています。大日本麦酒から日本麦酒へとわかれた際に、日本麦酒の初代社長に就任したのが柴田清です。日本麦酒は「サッポロ」と「ヱビス」の商標を継承するのですが、どちらも地域ブランドであったため、広がりを持たせると同時に大日本麦酒を継承する意味で、この社名となりました。
一時はこの柴田によって生産するビールもすべて「ニッポンビール」となるのですが、馴染みのないブランドに販売面で苦戦。1956年にサッポロビールを北海道限定で復活させます。極めて好調な売れ行きであったために、翌年1月には全国販売に踏みきりました。日本麦酒は1964年には社名もサッポロビールへと変更するのですが、つまり、現在のサッポロビールの下地をつくったのが、この柴田清ということになります。

●街歩きスポットその7:恵比寿の樹
次のスポットは、銅像からサッポロ広場を抜けた先、恵比寿ガーデンプレイスの北東の端にあるちょっと変わった形のモニュメント、「恵比寿の樹」です。日本最古のビヤホールとして今も営業を続けるサッポロライオン 銀座七丁目店を手がけた建築家、菅原栄蔵氏の作品で、実は銀座七丁目店にはここと同じものが今も2つ店内に置かれています。ビール工場が恵比寿ガーデンプレイスとして生まれ変わった際に、同じものをこの場所にモニュメントとして設置しました。
ガイド役の社員は昭和60年頃に撮影された恵比寿ビール工場の空撮写真を紹介しました。写真では敷地内いっぱいに建物が並び、見るからに手狭になっていることがうかがえます。このままでは伸び続けるビールの需要に対応しきれないと判断したサッポロビールは、工場の移転を決定し、千葉県船橋市に千葉工場をつくったのです。ちなみに工場があった当時、この北東の角にはトラックで商品を搬出する出入り口があったとのこと。今でもこの前の道は片側一車線の決して広いとは言えない道路。ひっきりなしに大きなトラックが出入りしていたとは少し考えにくいものがあります。周辺環境という意味でも、恵比寿ビール工場は限界に来ていたのですね。

●街歩きスポットその8:兜煙突
サッポロビール本社社屋の周囲を反時計回りにぐるっと一周する形で、一行は集合場所へと戻ってきました。次のスポットは、本社正面玄関に向かって左手にある兜煙突です。まるで西洋の兜のような形をしたこの金属製のカタマリは、麦芽を乾燥させる建物、製麦棟に設置されていたもの。ビールの主な原料は水、ホップ、大麦ですが、大麦のままではビールの醸造ができません。大麦を発芽させ、乾燥を行い麦芽をつくる「製麦」という工程が必要なのです。
製麦棟のなかは三層にわかれていて、下から熱風が噴き上がる構造になっていました。麦芽はまずいちばん上の層で徐々に温度をあげながら発芽を止めつつ乾燥させ、段階を追って下の層へと移されます。いきなり高い温度の風に当てると、麦芽のなかにある酵素の働きが失われてしまうため、このような手間をかけたのですね。
乾燥させるのが目的ですから製麦棟のなかは高い温度を保たなければなりませんが、同時に麦芽から出る水蒸気を外に放出する必要があります。外から雨や冷たい風が吹き込まないように排気する仕組みが、この兜煙突。実はこの兜煙突、風見鶏のように風向きによって向きを変え、開口部がつねに風下を向くようになっているのです。
現在、製麦はすべて群馬にある工場で行っていますが、以前はこうして工場内で行っていました。恵比寿工場の製麦棟は1974年に解体されてしまいます。設置されていた兜煙突は2体が現存していて、このサッポロビール本社前のほか、札幌市にあるサッポロビール園に残りのひとつが置かれているそうです。

■最後はYEBISU BREWERY TOKYOで乾杯!
屋外のスポットを一通り巡った一行は最後にYEBISU BREWERY TOKYOへ。この施設によって、恵比寿という街で36年ぶりにビールづくりが復活を遂げました。ヱビスビール記念館があったこの場所にYEBISU BREWERY TOKYOが開業したのは今年の4月。なかはヱビスビールの歴史をつづったミュージアムエリア、ビールの仕込釜が置かれたブルワリーエリア、そしてここでつくられたビールを実際に飲めるタップエリアと、3つのエリアで構成されています。
ブルワリーエリアに見える3つの設備のうち、右が仕込釜です。細かく砕いた麦芽にお湯を加え、このなかでどろどろのおかゆ状にします。すると、麦芽の酵素によってデンプンが発酵に適した糖へと分解されるのです。左がろ過に使われる釜です。ここで麦汁から要らないものを取り除きます。真ん中は煮沸を行う釜です。麦汁にホップを加えて煮沸をすることで香りや苦味が生まれ、さらに殺菌も行われます。その後、壁の奥にある遠心分離機で不要物が取り除かれたのち、地下の醸造場へと運ばれ、発酵、熟成、樽詰めが行われます。
YEBISU BREWERY TOKYOでは、1回で約1キロリットルの仕込ができます。350ミリリットル缶で換算すると、2850本分とのこと。主力工場の千葉工場では1回の仕込が120キロリットルですので、規模感が大きく違うことがわかりますね。ちなみにタップエリアには大きな銅製の釜が置かれていますが、これは1988年に恵比寿工場を閉鎖するまで使用していた釜で、1回に25キロリットルの仕込ができました。
1回の仕込量が少ないのはデメリットのように思えますが、逆に小回りが利くというメリットもあります。YEBISU BREWERY TOKYOではほぼ一月ごとに数量限定の新しいビールを提供できているのは、この規模だからこそ、という面があるのです。こうした説明を聞いた後、一行はテーブルに着き、YEBISU BREWERY TOKYOで通年販売されている「ヱビス∞(ヱビスインフィニティ)」で乾杯! 同じテーブルを囲んだ同士で交流を深めながら、街歩きイベントを終えたのでした。


昭和47年頃の恵比寿工場の様子を再現したジオラマ。(有料ツアー専用)ビールの製造には大量の水が必要になるため、敷地内には大きな貯水池がつくられていました。


↑タップエリアのカウンター両脇に立つ2本の柱。これは恵比寿工場の仕込室で使っていたもの。工場を閉鎖したときによくこれだけのものを壊さずに保存していたと驚かされます。


――今回の街歩きイベントで訪れたスポットは、一般の方でも自由に見ることができるところばかりです。恵比寿ガーデンプレイスにお立ち寄りの際は、この記事を参考に、ヱビスビールとサッポロビールの歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?
(写真・文=稲垣宗彦)