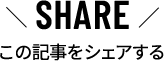CATEGORY : 遊ぶ
彼女がくれた座右の銘

「ねえ、どんな味だった?」
テーブルの向かいに座る彼女が、私の背伸びを見透かすように口角を上げて言った。テイスティングした白ワインは、どちらかといえば辛いけど、フルーティだと言われれば確かにそうとも思えて、「これで」と言うほかなかった。
恵比寿駅の東口から十分ほどのところにあるフレンチレストラン。ネットで調べた限りでは“アットホームな空間”と書かれていたのに、店内はロウソクの火の揺れさえ音として聞こえそうなほど、強固な静寂と緊張に包まれていた。
ちょっとした下心だった。彼女とは二年ぶりの再会で、私は自分が少し大人になったところでも見せてやろうと、服も店も、気合いを入れて選んだつもりだった。でも蓋を開けてみれば、どうだろう。
彼女は私より何倍も大人びていて、何十倍も美しくなっていた。一つ一つが僅かに違うデザインのネイル、昔は似合わなかったはずのグロス、長く伸びて巻かれた髪。どれも品があるし、今の彼女に似合いすぎている。私を過去に置き去りにするには十分な魅力を放っていた。
「じゃあ、乾杯」
薄い硝子でできたワイングラスに口をつける。その唇の動きすら、目で追ってしまう。彼女はこの二年でどんな経験をして、どんな失敗を経て、こんなにも美しくなったのか。社会人と学生って、そんなに違うものだろうか。「なんか、変わらないね」と懐かしむような目で言った彼女の言葉に、私は絶望しかけていた。
彼女とは、大学時代に所属していたインカレの学生団体で出逢った。専門学校に入学したばかりの彼女は、他の大学生には見られない、影のような深みを持っていて、私にはその暗闇がキラキラと光って見えた。
すぐに打ち解けた私たちは、笑いと怒りの波長がよく合った。二人で無名のお笑い芸人のライブを観に行ったり、ネットニュースの記事に憤ったりして過ごした。飲酒が許される年齢になれば、飲みに行くことも増えて、赤提灯の点いた店でビールグラスを何度も重ねる仲になった。数少ない、同い年の気が許せる飲み友達だった。
そんな彼女が専門学校を二年で卒業すると、大学に通う私より早く社会に出て、一カ月もしないうちに疎遠になった。就活を終えたことを理由に私から声をかけなければ、きっと二度と再会することもなかっただろう。刹那的で、希薄な関係。そう言われれば否定しようもない距離の人だった。
「慣れはさ、人を傲慢にするよね」
堅苦しい店が嫌だったのか、それとも私に気を遣ってくれたのか、食事を終えると私たちは早々に恵比寿の街に繰り出して、二年前に寄った赤提灯の店に場所を移していた。少し頬を赤くした彼女は、どこか眠たそうにも見えた。
「社会人になってさ、接待や付き合いで、高いお店に連れられることも増えて。なんか、舌が肥えたわけでもないのに、値段が高いものこそ、いいお酒って思うようになってさ」
彼女が先ほどのフレンチに満足していないことは、鈍感な私にもわかった。もっといい店に行く機会が何度もあったのだろうと、その時も感じた。
「でもこうやって冷えたジョッキで飲むビールがさ、さっきのワインより明らかに美味しく感じたりして。傲慢になってたんだなって思った。慣れは怖い。なんでもそうだね。慣れてくると、人を傲慢にさせちゃう」
彼女が少し声を大きくして言って、その後に見せた悲しそうな笑顔だけは、二年前の彼女に近いように思えた。
「あのさ、私も社会に出て、オトナになって、二人で高級なものを食べるようになってもさ、またこうやって、この店で飲もうよ。二人だけは傲慢な人間になんか、ならないようにさ」
私が言うと、彼女は静かに笑って頷いた。
あの夜から、また何年も、彼女には会っていない。
けれど、すっかりオトナになった今でも、「慣れは人を傲慢にする」という私の座右の銘だけは、時を止めたように変わらずそのままでいる。
この小説はサッポロビール公式ファンサイトSAPPORO STAR COMPANYにて、サッポロファンから寄せられたエピソードを基に制作されました。
▼企画
あなたの「忘れられない一杯」のエピソード募集! – SAPPORO STAR COMPANY | サッポロビール (sapporobeer.jp)
ぜひ公式ファンサイトSAPPORO STAR COMPANYでもお待ちしております!